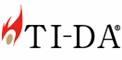15世紀頃の北方〈エゾ〉世界(1)
中世、日本の境界は“西は鬼界が島、東は外が浜”とされ、北方は外が浜(現在の青森)までが日本国の支配の及ぶ領域とされました。
鎌倉時代、この地域は日本国の守りの要所として北条氏の所領となり、代官の安藤氏が現地を掌握していました。安藤氏は前九年の役で源氏に滅ぼされた安倍氏の子孫を自称しており、「蝦夷管領」とも呼ばれた、北方世界における大きな勢力でした。ただし、安藤氏をはじめとしたこの頃の「和人」勢力はアイヌを完全に支配下に置いてはいません。アイヌ民族は一つの権力のもとに組織はされていませんでしたが、その勢力は蝦夷が島(北海道)のみならず千島・樺太方面、津軽半島まで拡大していました。樺太方面ではモンゴル元朝の軍勢とも衝突し、アイヌは海を渡って大陸の元軍も攻撃しています。この頃の国境は非常にあいまいなものであり、津軽半島などにも多数のアイヌが和人と混在している状況がありました。アイヌは狩猟民としての性格が強調されますが、それはむしろ北方の産物を調達するためであり、ラッコやサケ、昆布などの北方の産物を日本に供給する「交易の民」としての性格が強かったといえるでしょう。
13世紀後半になると、北方世界ではアイヌの反乱が多発、安藤氏一族の争いも加わり大混乱に陥ります。安藤氏の軍勢にはアイヌも動員されたようで、必ずしもアイヌ対和人という構図ではありませんでした。蝦夷大乱に鎌倉幕府は衝撃を受け、鎌倉では連日、蝦夷降伏の祈祷が行われます。外が浜は日本国の要衝であり、支配者である幕府の権威を地に落とすことになります。鎌倉幕府滅亡は、実はこの蝦夷内乱が大きな要因であったとされています。
南北朝の争乱の後、北方世界の支配者となったのは外が浜の
十三湊(とさみなと)を拠点とした安藤氏一族です。十三湊は北方世界最大の交易港で、北は樺太・ユーラシア大陸につながる蝦夷が島、南は日本海の越前から交易物資がここに集積されました。十三湊は琉球の那覇に劣らない交易都市だったのです。北方世界のメインルートは、それまでの奥大道の陸上交通から、日本海の海上交通へとシフトしていきます。北方世界の制海権を掌握し、交易の莫大な富を手にした安藤氏は自らを「日之本将軍」と称しました。日の本(ひのもと)とは日本のことではなく、太陽の出る東、つまり日本の東の果てを意味します。
また安藤氏は自らの先祖を安倍氏としただけでなく、征夷大将軍の坂上田村麻呂に討たれた悪路王や、天照大神に敵対する第六天魔王の孫、安日長髄(あびのながすね)の系譜を自称していました。日本の中央政権にとって外が浜は蝦夷(えみし)の住む野蛮で汚らわしい地でしかありません。しかし安藤氏はそのような差別的な言説を肯定的に受け入れることで、自らが由緒ある蝦夷の統率者であることを宣言し、北方世界の王者たらんとしたのです。
関連記事